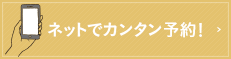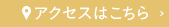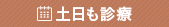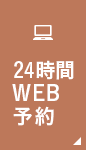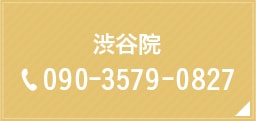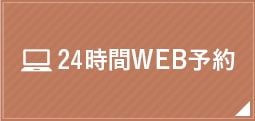肩こりの治療
頚椎の病変が原因の肩こりの場合
関連疾患

- ストレートネック
- 頚椎椎間板ヘルニア
- 頚椎症
頚椎の病変によって周りの筋肉の緊張が高まり、その結果血流障害を起こしてしまいコリ・痛みとして現れるのが頚椎の病変が原因の肩こりです。
長い期間この状態が続くと、身体にとってこの状態が当たり前になってしまうため、病変が落ち着いてきたとしても肩こりだけが残ってしまいます。飛び出たヘルニアはいずれ引っ込み保存療法でも回復していきますが周囲の血流が改善されず悪いままだと治りが悪くなってしまいます。
当院では柔軟性がある血流の良い状態を作り出すために周りの筋肉の緊張をほぐして炎症を抑えます。過剰な神経への刺激が肩こりの原因となってしまっていますが、それを軽減することで肩こりを起こしにくくしていくのです。改善するまでには多少時間のかかる頚椎の病変が原因の肩こりですが、だんだんと軽減させることが可能ですので、施術を数回だけして諦めてしまうのではなく、継続的に行っていくのがおすすめです。
姿勢が原因の肩こりの場合
関連する筋肉
- 大胸筋
- 小胸筋
- 大円筋
- 肩甲下筋
- 前鋸筋
- 僧帽筋
- 肩甲挙筋
- 広背筋
- 菱形筋
 悪い姿勢で多いのが猫背です。猫背になると前方に頭の重心が傾いてしまいますが、この時、頭が前に倒れてしまわないように首から背中側の筋肉は常に力が入っている状態になります。このため、特別何もしていないにも関わらず慢性的に肩が凝ってしまうという状態が起こるのです。特に、常に腕を前に出しっぱなしの姿勢になりがちなデスクワークが多いという人は肩が前側に入ってしまうため背中が丸まったような姿勢になります。肩こりというと肩から背中の硬さばかり気にかかりがちですが、実は原因となっているのは前に肩を引っ張っている前側や脇の辺りの筋肉が張っていることが原因。猫背の姿勢になってしまっているということが少なくありません。
悪い姿勢で多いのが猫背です。猫背になると前方に頭の重心が傾いてしまいますが、この時、頭が前に倒れてしまわないように首から背中側の筋肉は常に力が入っている状態になります。このため、特別何もしていないにも関わらず慢性的に肩が凝ってしまうという状態が起こるのです。特に、常に腕を前に出しっぱなしの姿勢になりがちなデスクワークが多いという人は肩が前側に入ってしまうため背中が丸まったような姿勢になります。肩こりというと肩から背中の硬さばかり気にかかりがちですが、実は原因となっているのは前に肩を引っ張っている前側や脇の辺りの筋肉が張っていることが原因。猫背の姿勢になってしまっているということが少なくありません。
そのような張りが身体に残っているといくら正しい姿勢を続けようとしても前の方に常に引っ張られてしまうので、正しい、背筋が伸びた姿勢を保ち続けるのが困難になってしまうのです。正しい姿勢を作りやすい身体を目指すためには肩から背中にかけての硬さをほぐすだけでなく、前側、脇の辺りの張りも取ってあげる事が必要です。
頸・肩周辺が原因の肩こりの場合
関連する筋肉
- 小胸筋
- 斜角筋
- 鎖骨下筋
- 僧帽筋
- 肩甲挙筋
- 大・小菱形筋
- 三角筋
- 頭・頸半棘筋
- 棘上筋、棘下筋
- 頭・頸板状筋
斜角筋症候群(斜角筋の硬さが原因)、肋鎖症候群(第1肋骨と鎖骨の隙間が原因)、頸肋症候群(頚椎の余分な肋骨が原因)、小胸筋症候群(小胸筋の硬さが原因)の4つの症候群の総称を「胸郭出口症候群」と言います。頸から肩にかけ神経の通り道が狭くなることや硬くなった周辺組織で圧迫されることによって引き起こされます。さらに、普段の姿勢が悪く神経の通り道が狭くなって圧迫されることでも起こることがあります。肩周辺のコリだけでなく肩周りが重くだるい、腕にかけて痛みやしびれを感じる、脱力感、熱感、冷感を感じるなどの症状があります。
斜角筋症候群、肋鎖症候群、頸肋症候群、小胸筋症候群とこれら胸郭出口症候群が原因となっている肩こりには神経の通り道を確保し組織の柔軟性を回復させることで圧迫の原因を緩和していきます。また、姿勢によって神経の通り道が狭くなってしまっている場合には姿勢を改善していくように努めます。
首、肩周辺の筋肉が疲労することによって起こる肩こりは様々なところに症状が表れます。首から背中にかけて凝りが出る場合、主に肩上部分に凝りが出る場合、首の前側に凝りが出る場合、肩甲骨周辺に凝りが出る場合など。また、これらの凝りがいくか複合して現れる場合もあります。
心因性の肩こりの場合
肩の筋肉を使いすぎた疲労で起こるだけでなく、常にストレスや緊張にさらされたことによって身体がこわばってしまい、肩こりが引き起こされる場合もあります。このような肩こりの場合は肩のみならず首から背中にかけて広い範囲で緊張や張りが見られます。後頭部や背中の張りは特に強く、背中がスジ状に張ったり、頭痛を引き起こすこともあります。
ストレスとは言っても周りの環境によるストレスが全てではありません。内向的な方、完璧主義だという方、何もせずにいるのがストレスで何かしていないと落ち着かないという方はもしかしたら自分で自分にストレスを与えてしまっている可能性もあります。大人しくしているのが性に合わないからと言って常に忙しくしていると脳はフル回転しているため交感神経ばかりが緊張します。すると末梢血管の血流が滞ってしまい、筋肉も常に緊張した状態になるのです。だから筋肉に疲労が蓄積しやすく、気づいた時には肩が凝っているということが起こります。
常に緊張状態になっているこのような方の場合、それが当たり前になっているため自分で緊張を抜くための方法がわからなくなってしまっている場合も少なくありません。ですので鍼灸治療では必要以上に緊張してしまっている身体を緩めてあげて、よりリラックス出来る身体を目指していきます。緊張が緩和されてリラックスが出来ているという証拠に、鍼灸治療を行った後は夜もぐっすり眠れるという患者様や、慣れてくると施術中も寝てしまうという方も多くいらっしゃいます。
その他の肩こりの場合
関連する筋肉
- 後頭下筋群(上頭斜筋、下頭斜筋、大後頭直筋、小後頭直筋)
肩こりは眼の疲れによっても表れやすいです。眼の動きに合わせ頭の位置を微調整する筋肉が後頭部にありますが、眼をいつも使っているという方は後頭部から首にかけて凝りが現れやすいです。
筋力が足りないことによる肩こりも最近では増加しています。昔は洗濯も洗濯板を使ってゴシゴシ洗ったり、箒を使った掃き掃除、床を雑巾がけしたりと日常生活の中でも頻繁に肩の筋肉を使っていました。しかし現代では人間ではなく機械がこれらの作業を行うようになったことで、極端に肩周りの筋肉を使う機会は減り、筋力が低下しているのです。筋力不足によって腕を肩甲骨から釣り上げている筋肉がすぐ疲れてしまうので肩こりが起こりやすくなります。
また、他の病気が原因となって引き起こされる肩こりも存在しています。何もしていなくても強い痛みを感じる、日増しに症状が強くなっていくなどの肩こりがある場合は一度病院で診てもらうといいかもしれません。
肩こりの痛みの仕組み
「肩こりの痛みの負のスパイラル」の仕組みについてご説明したいと思います。
肩周りの筋肉疲労の蓄積によって乳酸ヒスタミンセロトニンなどが蓄積し、それが痛みや凝りを引き起こします。痛みが凝りは更に交感神経の緊張を増加させ、血管を圧迫。そうすることで血流障害が起こりますが、それが最初の肩周りの筋肉疲労の蓄積に繋がるため、負のスパイラルが完成してしまうのです。
よくある症状だからと軽くみられてしまいがちな肩こりですが悪化すれば頭痛、耳鳴り、吐き気、めまい、更に他の症状を引き起こしてしまう原因にもなる可能性があります。日常生活に支障が出てしまうことも多々あるため、快適な日常生活のためにも悪化する前にしっかりと解消することが大切です。